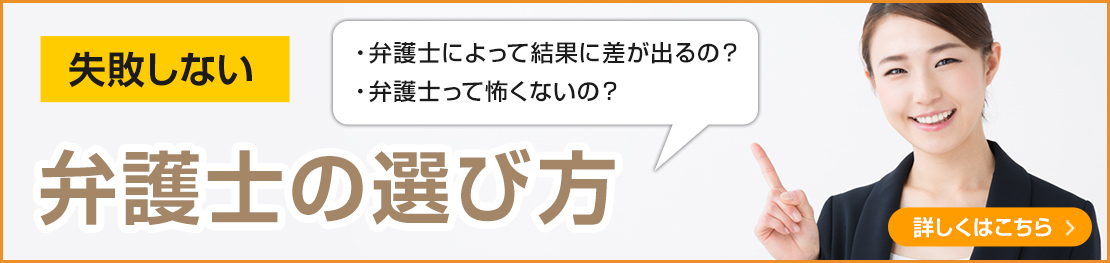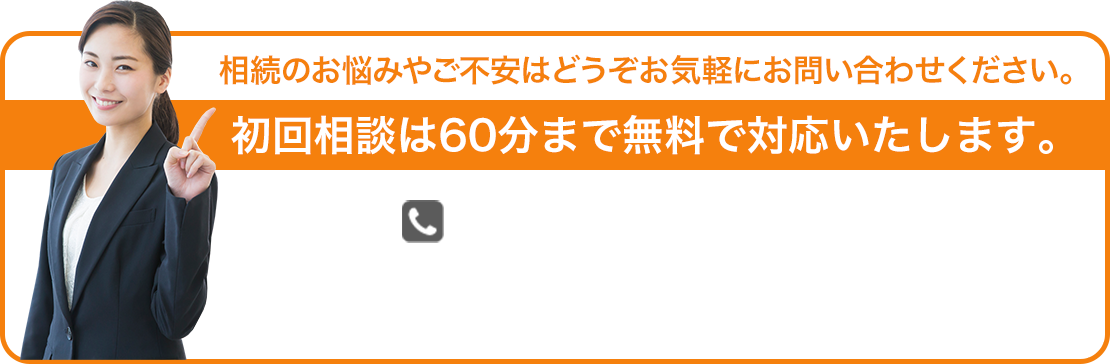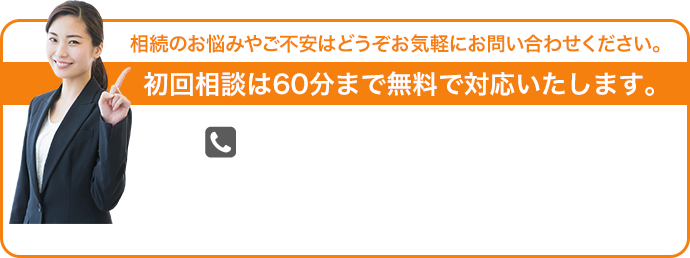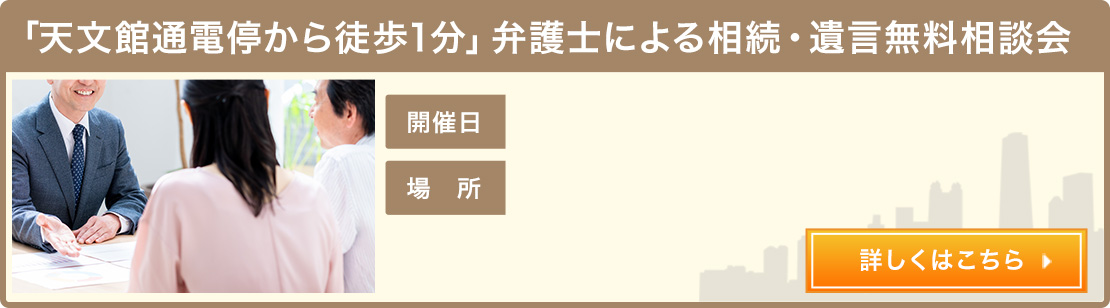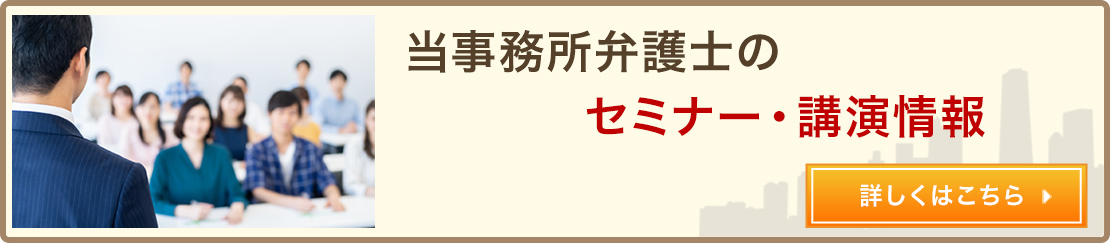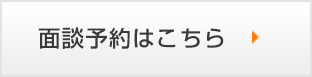特別受益と寄与分
遺言書がない場合、遺産分割は基本的に、法律の規定に基づく割合で分割されます(これを「法定相続分」といいます。)。したがって、相続問題は、争いようがないとも思えてしまうかもしれません。
しかし、法定相続分を修正する事柄として、特別受益と寄与分という問題があります。
そしてこの、特別受益と寄与分の問題が、実際の遺産分割の事例において、紛争の原因となっていることが少なくありません。
特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。
根拠規定は民法第903条です。
例えば、相続人のうちの1人が、被相続人から、生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションを買ってもらった、などの場合があります。
このような場合、これを「遺産の前渡し」とみなして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることになります。なぜなら、法定相続分は基本的に相続人間の公平性を担保するものですが、ある相続人が、「遺産の前渡し」分と共に、法定相続分をもらえば、かえって相続人間の公平性をそこなう結果になるからです。
算定例
被相続人の遺産が1億円で、相続人が子2人(長男、次男)であり、長男だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合。
1億円の遺産を単に子2人に分けるだけとなり、子の相続分は子の数での頭割りですから、1億円÷2=5000万円ずつ相続となります。
しかし、長男は2000万円の贈与を受けていますから、実質的に7000万円(2000万円+5000万円)受け取ることになり、公平性をそこないます。
特別受益がある場合の基本的な考え方は、特別受益分を、遺産総額に加算して(加算した後の遺産を「みなし遺産」と一般にいわれます)、法定相続分で分け、その金額から、特別受益を受けた相続人の相続分から、特別受益分を差し引きます(民法第903条第1項)。
【計算式】
みなし遺産 = 遺産:1億円+2000万円(長男の特別受益)=1億2000万円
長男の相続分:1億2000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円(+2000万円の贈与)
次男の相続分:1億2000万円 × 1/2 =6000万円
となります。
特別受益とみなされる可能性がある事例
民法第903条第1項において、特別受益の対象とされているのは、以下の通りです。
①遺贈
②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの
婚姻の際の持参金などが含まれます。
③生計の資本としての贈与
住宅購入資金、開業資金、事業資金など。
他方で、故人が生前に、特定の相続人だけに財産を渡している場合には、何らかの事情がある場合があり、故人が、形式的公平性を保たないことをかえって求めている場合もあり得ます。
上記の「(具体例)」では、例えば、故人と次男はもともと折り合いが悪かった、あるいは、故人は長男に特別な役割を希望しているなどがあり、それが生前の贈与につながっていた場合です。
このような場合も、特別受益の規定によって、修正することは、かえって故人の意思に反するものですから、故人が特別受益の規定による調整を求めない意思表示(これを「持戻し免除の意思表示」と言います)が認められれば、特別受益による調整を否定することができます(民法第903条第3項)。
しかし、この持戻し免除の意思表示を立証することは、容易ではありません。なぜなら、争いになるときに、故人はすでにおらず、確認しようがないからです。
また、書面等の客観的なもので、持戻し免除の意思表示が示されることも少ないです。なぜなら、そのような場合には、そもそも遺言書が作成されることが多いからです。
どのような場合に特別受益が認められるのか、また、上述した持戻し免除が認められるべきかは、具体的な事例によって詳細な検討、調査そして主張立証を経て初めて明らかな判断が得られることが少なくありません。
納得が出来ない点やご不安な点がある場合、特別受益を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。
寄与分とは
寄与分とは、相続人の中で、事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産形成または維持や増加に特別の寄与をした人に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です(民法第904条の2)。
ここで重要なのは、「特別の」寄与であることです。具体的には、無償であること(対価を得ていないこと)、親族間の法律上の扶養義務等を越えていることが必要になります。
具体例
被相続人の遺産が1億円で、相続人が子2人(長男、次男)であったところ、長男が家業を手伝って、被相続人の財産形成に1000万円の寄与があった場合
見なし遺産 = 遺産:1億円-1000万円(長男の寄与分)=9000万円
長男の相続分:9000万円 × 1/2 + 1000万円 = 5500万円
次男の相続分:9000万円 × 1/2 =4500万円
となります。
寄与分とみなされる可能性がある事例
- 相続人が、被相続人である親の家業に従事して、財産を増やしていた
- 相続人が、親の介護をして介護費用の支出を抑えていた
このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
寄与分について争いが生じた場合、それが認められるためには、寄与分の基礎となる事実を、証拠と共に具体的に立証していく必要があります。
しかし、それを立証していくことは、困難であることが多いです。例えば、介護の事実ですが、事後の相続紛争に備えて、ご自分で介護記録を記入して作成したり、介護の状況をすべて録画したりする人も少ないと思います。
また寄与分が認められたとしても、それが具体的にいくらと算定するかは、また別の問題です。
したがって、どのような証拠を集めるか、どのように算定するかは、相続問題に精通した弁護士に相談し、助力を得ることが、解決の近道といえます。
寄与分問題、特別受益問題は弁護士にご相談ください
注意が必要な類型としては、寄与分が認められるのは、法定相続人に限られます。例えば、上述の「(具体例)」において、長男の配偶者が、被相続人の生活費を補填したというような場合には、寄与分を主張することはできません。相続人ではないからです。
ただし、近時の民法の改正によって、法定相続人等ではない被相続人の親族が、被相続人の療養看護その他の労務の提供をして、被相続人の財産の増加及び維持に貢献していた場合(このような貢献をした被相続人の親族を「特別寄与者」といいます。)に限り、「特別寄与料」を相続人に請求することが可能です(民法第1050条)。
また、特別寄与料の請求期限は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知ったときから6か月を経過するまで、または相続開始のときから1年を経過するまでと定められております(民法第1050条第2項)ので、こちらも注意が必要です。
また、上述の「(具体例)」において、長男の配偶者が、被相続人の生活費を補填していたような場合であっても、被相続人の相続発生時に既に長男と離婚している場合には、「被相続人の親族」ではなくなり、「特別寄与者」に該当せず、特別寄与料を相続人に請求することができません。このようなことが考えられる場合には、長男の配偶者が長男との離婚時に長男と財産分与、慰謝料などの離婚条件を詳しく協議して合意することや、被相続人が長男の配偶者へ生前贈与を行ったり、遺言で遺贈を行ったりすることで、被相続人の生活費を補填してくれたことに報いることが考えられますので、弁護士に相談することをおすすめします。